コラム

コラム
2025年8月28日
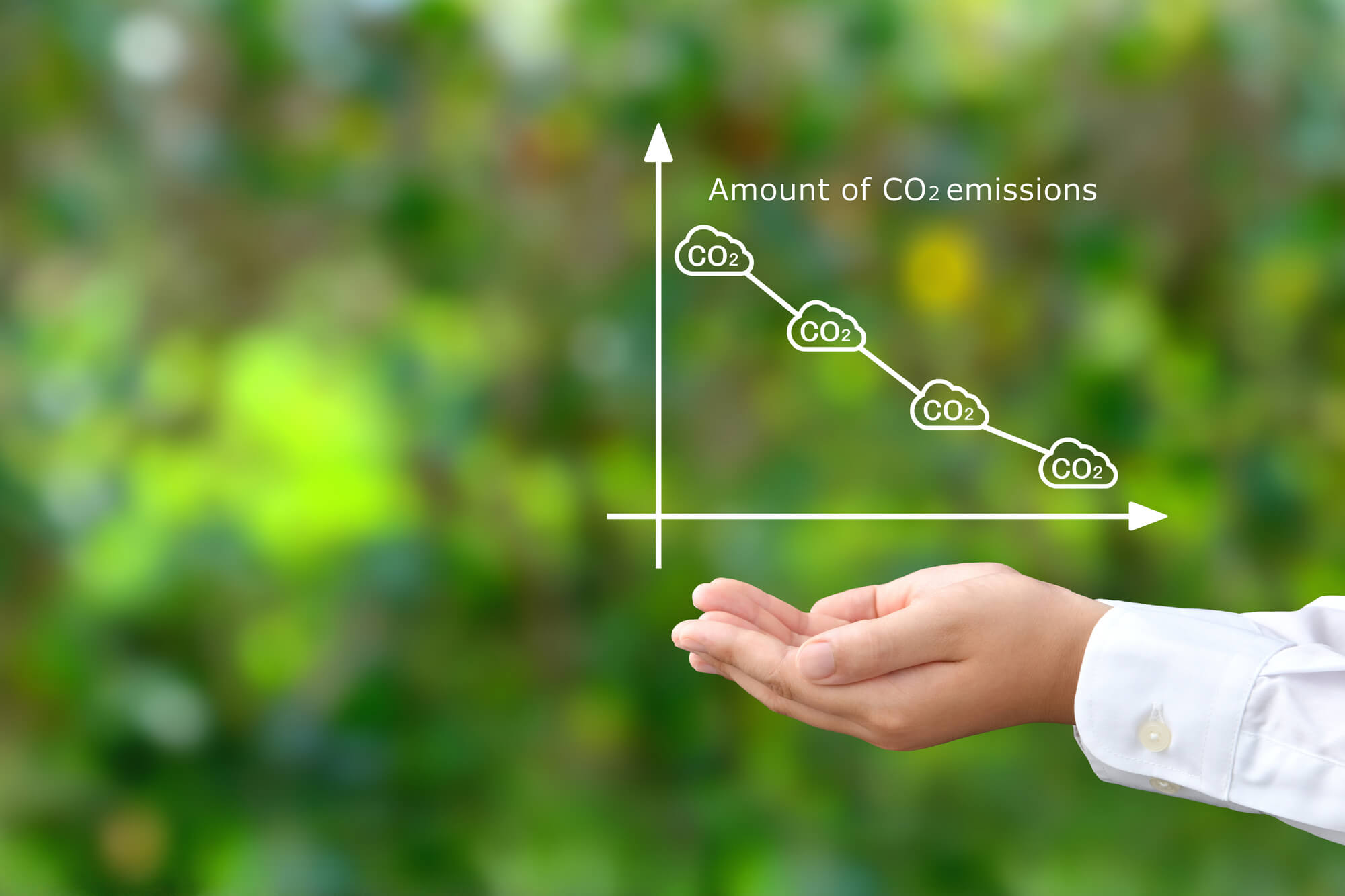
製造業を取り巻く環境が大きく変化する中、工場におけるCO2削減の重要性が高まっています。企業の持続的な成長や取引先との関係強化、社会的評価の向上など、CO2削減には多くのメリットがあります。
一方で、具体的な対策が分からなかったり、コストやノウハウが不足していたりと課題に直面している工場も少なくありません。本記事では、工場のCO2削減方法とメリット、取り組む際の課題について解説します。
目次
経済産業省の調査によると、71.4%の中小企業が、なんらかの形でCO2排出量削減に取り組んでいるという結果が出ています。これは、2050年カーボンニュートラルに向けた国の方針が浸透し、企業規模を問わず環境配慮が求められていることの表れです。
具体的な取り組みとしては以下のとおりです。(複数回答、n=2,139)
| 省エネ型設備への更新・新規導入 | 40.0% |
| 運用改善による省エネの推進 | 38.0% |
| エネルギー使用量・温室効果ガス排出量の把握・測定 | 25.0% |
| 自家消費型太陽光発電の導入 | 12.3% |
| 脱炭素関連ビジネスの展開 | 7.9% |
| その他の取り組み | 21.7% |
| 取り組みは行っていない | 28.6% |
多くの中小企業が照明のLED化や高効率空調設備の導入、設備運転の最適化といった「省エネルギー」を中心に着手しています。大がかりな設備投資が難しい企業でも、エネルギーの見える化や従業員への省エネ教育など、工夫次第で実現可能な施策は多いです。
こうした取り組みの背景には、コスト削減効果に加えて、取引先や顧客からの環境対応要請が強まっていることがあります。特に製造業では、サプライチェーン全体での環境対応が求められており、脱炭素に後ろ向きな企業は取引先から外されるリスクも無視できません。
参考元:中小企業の脱炭素推進に向けた現状と課題|日本・東京商工会議所
工場がCO2削減に取り組むことは、単なる環境貢献にとどまりません。経営面でも多くのメリットをもたらす施策であり、長期的な競争力強化にもつながります。工場がCO2削減に取り組むメリットを紹介します。
CO2排出量の多くは、電気・ガス・燃料などのエネルギー使用に起因します。そのため、工場内のエネルギー効率を高めることで、CO2排出を抑えると同時に光熱費や燃料費を削減することが可能です。
例えば、モーターやコンプレッサーの高効率化、空調や照明の最適化、ボイラーの定期メンテナンスなど、既存設備の見直しによって大きなコスト削減効果が得られます。中小規模の工場であっても、年間で数十万円から数百万円規模のエネルギーコスト削減が可能となる場合もあり、CO2削減が直接的な経済的メリットにつながる点は見逃せません。
実際に経済産業省の調査結果では、光熱費・燃料費の削減に取り組んでいる中小企業が75.2%ともっとも多いです。省エネとCO2削減は、日々の積み重ねが成果に直結する分野です。早い段階から取り組むほど、長期的なコスト競争力の確保につながります。
環境意識の高まりとともに、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まっています。CO2削減に積極的な工場は、社会や地域から環境に配慮した企業として評価されやすくなり、企業ブランドの向上につながります。特に消費者向け製品を扱うメーカーにおいては、環境配慮型製品の開発・製造がブランド力強化に直結しやすいです。
また、自治体や商工会議所などの表彰制度に選出されるケースもあり、こうした外部評価が新たな販路開拓や採用活動にも好影響を与えます。SDGsやESG投資といったグローバルトレンドの中で、企業のイメージは取引先の選定要因にもなっているのです。
世界的なカーボンニュートラルの流れを受け、産業界全体が急速に脱炭素へと舵を切っています。この流れは一時的なものではなく、むしろ今後さらに強まっていくことが予測可能です。工場がCO2削減に早期から取り組んでおくことで、設備やプロセスの脱炭素化を段階的に進められ、急な制度変更や技術変化に対しても柔軟に対応できます。
例えば、再生可能エネルギーの導入や電動設備への転換など、新技術の普及は加速度的に進んでおり、こうした変化を見越した準備が不可欠です。加えて、炭素税の導入や排出権取引制度など、コスト構造そのものが変化する可能性もあります。
今後の不確実性を考慮すると、環境対応はリスク回避と同時に、変化に強い組織体制を作る手段ともいえます。市場の変化に柔軟に対応できる工場こそが、今後の競争を生き抜く存在になるでしょう。
脱炭素化の取り組みは、今後ますます厳格な法規制の対象となっていくと予測されます。実際にEUでは「CBAM(炭素国境調整措置)」が導入され、日本でもCO2排出量の開示や削減義務が拡大する方向です。今のうちからCO2削減に着手しておけば、将来的に新たな環境規制が施行された際もスムーズに対応できます。
特にエネルギー使用量の多い工場では、省エネ法や温対法などによる定期報告義務、管理体制の整備、監査対応が求められることもあり、対応準備の有無が企業間の差を広げます。
すでに多くの自治体では、補助金申請の要件としてCO2削減計画の提出を求める制度が多くあるのが現状です。今後はこうした制度がより広範に導入されたり、規制として義務化されたりする可能性もあるため、早期に対応を進めておくことで、法令や制度の変化にも柔軟に対応できます。
経済産業省の調査によると、企業の約4社に1社が取引先からCO2削減に関する要請を受けており、中でも「温室効果ガス排出量の把握・測定」を求められた企業は13.8%ともっとも多い結果となりました。これは、サプライチェーン全体のカーボンフットプリントを削減する動きが背景にあります。
中小企業であっても、環境対応の一翼を担うことが求められる時代です。特に製造業や物流業では、CO2排出量の管理状況が調達先の選定基準に組み込まれていることも少なくありません。こうした流れに対応するためには、早い段階で自社の排出状況を把握し、削減方針を明確にしておくことが重要です。
エネグラフを活用すれば、CO2排出量の見える化と削減効果の定量的な把握が可能になります。取引先からの信頼を得る上でも、こうしたツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
環境意識の高まりとともに、企業のサステナビリティへの取り組みは採用活動にも影響を及ぼしています。特に20代・30代の若手層を中心に、環境配慮に積極的な企業に対して好印象を持つ傾向が強まっています。企業選びの際に、給与や福利厚生だけでなく、社会的意義や企業姿勢を重視する人材が増えているのです。
そのため、CO2削減への取り組みは、単なるコスト削減策ではなく、環境配慮に取り組む企業というブランディングの一部としても機能します。実際に、自社の環境活動を採用ページや求人票で具体的にアピールしている企業も増えています。
また、SDGsやESGに関心のある学生や転職希望者にとって、CO2排出量の見える化や削減目標の明示は、企業への信頼感につながるポイントです。
工場でのCO2削減は、コスト削減や企業価値の向上につながる一方で、実際の現場では多くの中小企業が課題を抱えています。工場がCO2削減に取り組む際の課題について詳しく紹介します。
これまでCO2削減に取り組んでいなかった企業の多くは、CO2削減に関する具体的なノウハウが社内に蓄積されていません。例えば、「どの設備を見直せばいいのか」「どのような取り組みが削減につながるのか」が明確でないため、行動に移すことができないのです。
専門の人材がいない場合、外部のコンサルタントに依頼する選択肢もありますが、費用面や判断の難しさから、導入をためらう企業も少なくありません。まずは、自治体の支援制度や省エネ診断など、無料・低コストで利用できる情報を収集するところから始めてください。
CO2削減に取り組むには、まず現状の排出量を正確に把握する必要があります。しかし、電気・ガス・燃料など、複数のエネルギー源を扱う工場においては、排出量の算定が複雑になりがちです。特にScope1(自社の直接排出)やScope2(購入電力由来の排出)といった区分に対応するには、一定の知識とツールが必要になります。
こうした算定業務を自力で進めるのは難しいと感じる企業には、エネルギー管理ツールの導入がおすすめです。例えば、センサーやエッジデバイスを設置するだけでCO2排出量を自動で見える化できるツールなどを利用しましょう。
CO2削減のためには、省エネ設備への投資やデジタルツールの導入が必要になるケースがあります。しかし、中小企業ではその初期費用を捻出するのが難しいという声も多いです。特に設備の更新やエネルギーマネジメントシステムの構築などには、数百万円単位の支出が発生することもあります。
このような資金面の課題に対しては、国や自治体が実施する補助金や助成制度を活用することが有効です。中小企業に役立つ補助金に関しては、以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。
関連記事:【2025年最新】中小企業に役立つ省エネ補助金をエリア・設備別に紹介
工場でCO2を削減するには、具体的かつ継続的な対策が求められます。単に電力使用を減らすだけでなく、エネルギーの質や使い方を最適化することで、効率よく排出量を抑えることが可能です。工場でおすすめのCO2削減方法について紹介します。
まず取り組むべきは、工場内のエネルギー使用状況を「見える化」することです。どの設備が、いつ、どれだけ電力を消費しているのかが分かれば、無駄を発見しやすくなります。エネルギーのロスが起きている箇所を特定できれば、改善ポイントも明確になるでしょう。
例えば、エネルギー管理システム(EMS)やIoTセンサーを導入することで、設備ごとの消費量をリアルタイムでモニタリング可能です。エネグラフを使えば、CO2排出量まで自動的に把握できます。可視化によって、数値に基づくPDCAを回せるようになる点が大きな利点です。
古い機械設備や空調システムは、消費エネルギーが大きく、結果としてCO2排出量も多くなりがちです。最新の省エネ機器に更新することは、即効性のあるCO2削減対策です。例えばインバータ付きのモーターや高効率ボイラーに切り替えることで、大幅な電力削減が可能になります。
補助金制度を活用すれば、初期投資の負担を軽減しながら最新設備の導入を実現できます。補助対象となる設備や機器も多く、CO2削減と生産性向上を同時に実現できるチャンスです。まずは既存設備のエネルギー効率を点検し、入れ替えの優先順位を整理してみてください。
CO2排出を根本から見直すには、使用する電力そのものを再生可能エネルギーに切り替えることも有効です。近年では、太陽光発電や風力発電、バイオマス電力など、環境負荷の少ない電源を積極的に採用する企業が増えています。
自社敷地に太陽光パネルを設置する方法もありますが、初期費用や設置スペースに不安がある場合は、「再エネ由来の電力プラン」に切り替えるのも方法の一つです。すでに多くの電力会社がCO2フリー電力の提供を始めており、契約変更だけで実質的なCO2削減が可能になります。
生産スケジュールや運転計画を見直すことで、不要な稼働時間や待機電力を削減できるケースは少なくありません。例えば、設備のアイドルタイムや生産ラインの空き時間が長い場合、無駄な電力消費が発生している可能性があります。
設備ごとの電源管理やスケジューリングの最適化、センサーを活用した自動制御などを導入することで、稼働のムダを可視化し制御しやすくなります。また、シフト調整や稼働の平準化によっても、CO2排出量の削減に貢献できるでしょう。
照明は工場の電力消費に占める割合が大きく、LED化による省エネ効果は非常に高いです。従来の蛍光灯や水銀灯に比べて、LED照明は消費電力を約50%以上削減できる上、寿命も長くメンテナンスコストも抑えられます。
全体のCO2削減という観点でも、LEDへの全面切り替えは手軽かつ効果の高い対策です。特に24時間稼働する工場では、照明にかかるエネルギー量が膨大になるため、その分、削減効果も大きくなります。補助金の対象にもなりやすいため、コストを抑えて導入できる可能性があります。工場の電気代を節約する方法を以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
関連記事:工場の電気代の削減方法!内訳や相場、計算方法について解説
削減努力を続けてもなお排出されるCO2に対しては、カーボンオフセットの導入が有効です。これは、排出量に相当するCO2をほかの場所で吸収・削減する取り組みに投資することで、実質的な排出ゼロを目指す仕組みです。
具体的には、森林保全事業や再エネ事業へのクレジット購入を通じて、自社排出量と相殺します。実質ゼロの実現だけでなく、環境への積極的な姿勢をアピールする手段としても活用できます。特に大企業との取引やESG評価を意識する場合は、「削減+オフセット」の両輪で対策することが重要です。
工場のCO2削減に関するよくある質問を紹介します。
国や自治体では、CO2削減に取り組む事業者向けに多くの補助金や支援制度を用意しています。例えば、経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」では、省エネ機器の導入にかかる費用の一部が補助されます。
また、東京都が実施する「需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業」では、CO2削減につながるエネルギーマネジメントシステムの導入などが支援対象です。多くの制度では「CO2削減計画」の提出が要件となるため、早い段階から計画策定を進めておくとスムーズです。
制度の内容や対象要件は年度によって変わるため、こまめに各自治体や補助金ポータルサイトを確認するようにしましょう。
排出量は業種や工場の規模によって異なりますが、エネルギー起源のCO2排出量だけで見ても、日本全体の約30%を産業部門が占めています。特に製造業の中でも鉄鋼、化学、機械、食品などはエネルギー消費が多く、排出量も高い傾向があります。
CO2削減は今や一部の大企業だけの取り組みではなく、中小企業を含めたすべての事業者にとって重要な経営課題です。実際、約7割の中小企業がすでになんらかの形で削減に取り組んでおり、補助金制度や取引先からの要請など、環境対応を後押しする外部要因も増えつつあります。
工場でCO2削減に取り組む際は、エネルギー使用量とCO2排出量の「見える化」から始めるのがおすすめです。エネグラフは、既存設備にエッジデバイスを設置するだけで、エネルギー使用量とCO2排出量をリアルタイムで可視化できるツールです。ぜひ導入をご検討ください。

太平洋工業(株)新規事業推進部
【販売・利用申込み・
契約に関するお問い合わせ】
営業企画グループ
【製品に関するお問い合わせ】
(操作・設定、故障・不具合等)
プロダクトサポートグループ
受付時間:営業時間内(平日9-12時、13-17時、指定休業日除く)